2025年、企業を狙うマルウェアはさらに巧妙かつ多様化しています。従来のアンチウイルスだけでは検知が困難なファイルレス攻撃や、サプライチェーンを利用した攻撃が増加しており、企業は多層防御の実装と継続的な運用が不可欠です。
サプライチェーン攻撃・ランサムウェアによる「二重の脅迫」・ファイルレス/ゼロデイ攻撃が増加しており、セキュリティ対策は一時的な投資では済まない「継続的な取組み」が重要となっています。
![]() 目次
目次
OKWAVEに寄せられるマルウェアのお悩み
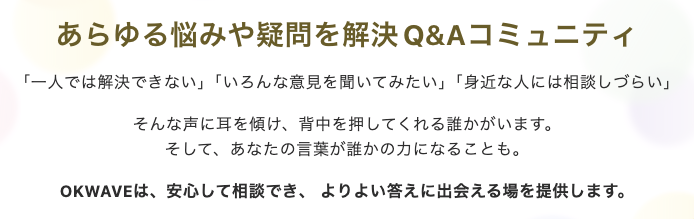
近年、サイバーセキュリティの脅威は急速に進化しており、特に「マルウェア」による被害は企業経営における最大の懸念事項の一つとなっています。
従来のウイルス対策だけでは防ぎきれない巧妙な手口が横行し、企業の情報セキュリティ体制は常に厳しい状況に置かれています。
実際に、OKWAVEにも「マルウェア」に関する多くの質問が日々寄せられています。
「2025年現在、どのようなマルウェア被害が流行しているのか?」
「自社が今すぐ取るべきマルウェア対策の具体的な事例を知りたい」
とお考えのユーザー様や企業担当者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年におけるマルウェア被害の最新動向を分析し、特に企業が直面している具体的なリスクを解説します。
そして、これらの脅威から企業資産を守るために「今」導入すべき、効果的なマルウェア対策の事例を具体的にご紹介します。この記事を通じて、貴社のセキュリティ戦略をアップデートするヒントが得られるはずです。
2025年におけるマルウェア被害の最新動向と傾向

2025年を迎えるにあたり、サイバー攻撃者はその手口をさらに巧妙化させています。もはや、マルウェア被害は特定の業種や大企業だけのリスクではありません。
サプライチェーンの弱点やリモートワーク環境を狙った攻撃が増加し、すべての企業が「いつ感染してもおかしくない」状況にあります。
ここでは、企業が特に警戒すべきマルウェア被害の最新動向と、その深刻な傾向について解説します。これらの動向を理解することが、適切なマルウェア対策を講じるための第一歩となります。
増加するランサムウェア攻撃と「二重の脅迫」
警察庁の「令和6年におけるサイバー犯罪情勢報告」によると、2024年のランサムウェアの被害報告件数は 222 件と高水準でしたが、2025年においてもランサムウェアは、企業にとって最大の脅威と言えるマルウェア被害の一つです。
(出典:警察庁 サイバー企画課 / 令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について)
単にファイルを暗号化して身代金を要求するだけでなく、盗み出した機密情報を公開すると脅す「二重の脅迫」の手口が常態化しており、被害がより深刻化しています。
一度感染すると、経済的損失だけでなく、情報セキュリティ上の信頼回復が極めて困難になる事例が多数報告されています。
最近では、アサヒグループホールディングスがランサムウェアによるサイバー攻撃を受けました。ニュースにも大きく取り上げられたので、記憶に新しい人も多いはず。この事例は、ランサムウェア攻撃が身近に迫っていることを実感させられる一件でもあります。
サプライチェーン攻撃を狙うマルウェアの脅威
大手企業だけでなく、セキュリティ体制が比較的脆弱な取引先や関連会社を踏み台にする「サプライチェーン攻撃」も、マルウェア被害の主要なトレンドです。
システム開発環境やソフトウェアのアップデート経路にマルウェアを仕込み、そこから最終ターゲットへ感染を広げる手口は、高度化の一途を辿っています。
この手口は、自社の対策だけでは防ぎきれないという点で、新たな情報セキュリティリスクとなっています。
ファイルレスマルウェアや未知の脅威(ゼロデイ攻撃)の台頭
従来のアンチウイルスソフトが検知の基準としてきた「ファイル」を使用せず、メモリ内や正規のシステムツールを利用して活動する「ファイルレスマルウェア」が増加しています。
また、セキュリティホールが発見されても修正プログラムが提供されていない状態を狙う「ゼロデイ攻撃」も、マルウェア被害の深刻な要因です。
これらは既知のパターンに依存する対策では捕捉が難しく、新しいマルウェア対策技術が求められています。
企業が今とるべきマルウェア対策事例:最新の脅威に対抗する多層防御戦略

2025年の高度なマルウェア被害に対抗するためには、複数の防御レイヤーを設ける「多層防御」戦略が不可欠です。
ここでは、最新の脅威に対応するための具体的なマルウェア対策の事例をご紹介します。
侵入経路の防御強化:ファイル無害化技術の活用
メール添付ファイルや外部から取り込むデータは、マルウェアの主要な侵入経路です。ファイル無害化技術(CDR:Content Disarm and Reconstruction)は、受信したファイルの安全性を徹底的に高めるマルウェア対策です。
これは、ファイルを「無害化」(サニタイズ)し、マルウェアが潜む可能性のある実行可能な要素やアクティブコンテンツ(マクロなど)をすべて除去し、安全なデータ部分のみでファイルを再構築する技術です。
この事例は、パターンマッチングに依存せず、未知のマルウェアやゼロデイ攻撃のリスクを根本から低減できるため、特に情報セキュリティを重視する企業で導入が進んでいます。
エンドポイントの可視化と迅速な対応:EDRの導入事例
マルウェアがエンドポイント(PC、サーバーなど)に侵入した後の挙動を監視し、迅速に対応するためのマルウェア対策がEDR(Endpoint Detection and Response)です。
EDRは、不審なプロセス実行やネットワーク通信をリアルタイムで検知・記録・分析することで、従来の対策をすり抜けたマルウェアに対しても、その活動を早期に発見し、隔離・対処を可能にします。
これにより、被害の拡大を最小限に抑え、感染経路の特定も容易になるため、現代のマルウェア対策において必須の事例とされています。
人による防御壁の強化:継続的なセキュリティ意識向上教育
どんなに技術的な対策を施しても、従業員によるヒューマンエラーがマルウェア被害のきっかけになるケースは後を絶ちません。
マルウェア対策を成功させるための誤解と継続的なセキュリティ投資の重要性

最新のマルウェア対策技術を導入したとしても、その運用や考え方に誤解があると、十分な効果を発揮できません。特に情報セキュリティの世界では、「一度やれば終わり」という考え方は通用しません。
ここでは、企業が陥りがちなマルウェア対策に関する誤解を明らかにし、長期的にマルウェア被害から企業を守るために不可欠な「継続的な投資」の重要性について解説します。
対策を成功に導くために、ぜひご確認ください。
「境界型防御」への過信という誤解
これまでの情報セキュリティ対策は、社内ネットワークと社外ネットワークの境界線(ファイアウォールなど)で防御する「境界型防御」が中心でした。
しかし、クラウドサービスの利用増加やリモートワークの普及により、この境界線は曖昧になっています。
もはや「社内=安全」という前提は通用せず、すべてのアクセスを検証する「ゼロトラスト」の考え方に基づき、社内のシステムに対してもファイル無害化のような厳格なセキュリティを適用することが、2025年におけるマルウェア対策の基本とされています。
セキュリティ対策は「一度きりの投資」ではない
マルウェア攻撃は進化し続けるため、マルウェア対策も継続的な見直しと投資が必要です。
セキュリティソリューションの導入費用だけでなく、運用のための人員や、最新の脅威動向に対応するためのシステムのアップデート費用も予算に組み込むことが、長期的に企業をマルウェア被害から守る鍵となります。
進化するマルウェア被害から企業を守るために

この記事では、事例を含めたマルウェア被害の最新動向と、これに対抗するために企業が今すぐ取るべきマルウェア対策の具体的な事例について解説しました。
2025年現在、企業が直面する脅威は、従来型のアンチウイルスソフトだけでは防げない、高度で巧妙なものとなっています。
特に、侵入前の水際で未知のマルウェアを無力化するファイル無害化技術や、侵入後の対応力を高めるEDRの導入は、効果的なマルウェア対策の核となると言えます。
おすすめのセキュリティソフトを知りたい方へ
これらの最先端のマルウェア対策の中核をなす技術について、さらに深掘りしたいユーザー様・企業担当者様もいますよね。
以下の記事では、多くのユーザーや企業に選ばれている「MetaDefender Core」をご紹介しています。
本記事でも触れたファイル無害化(CDR)やマルチスキャンといった具体的な機能が、いかにして企業をマルウェア被害から守り、情報セキュリティ体制を堅牢なものにするのかを詳細に解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
▶ MetaDefender Coreで企業の情報セキュリティは万全!マルウェア対策の重要性について解説
関連記事
-

2025.12.18
【市場調査レポート】「ブーム」から「文化」へ。なぜ今、人々は「高級食パン」ではなく「コッペパン」を選ぶのか?
-

2025.12.18
利益率20%も可能?コッペパン専門店フランチャイズの収入実態とコッペんどっとの強み
-
.png&nocache=1)
2025.12.18
コッペパン専門店に将来性はある?ブーム終了説の真実と10年続く経営戦略とは?
-

2025.12.18
未経験でもコッペパン専門店を開業できる?失敗を防ぐ方法とコッペんどっとの事例
-

2025.12.18
コッペパン専門店フランチャイズを徹底比較!初期費用・利益率・サポートで選ぶ「成功するFC」の見極め方
-
.png&nocache=1)
2025.12.18
【コッペパン専門店】失敗・撤退のリアルな理由とは?「コッペんどっと」で見る対策と生存の法則
-

2025.12.18
コッペパン専門店の開業資金はいくら?初期費用の内訳とコッペんどっとでコストを抑える秘訣
-

2025.11.24
UCプラチナカードの評判や口コミは?特典・審査・メリットなどを徹底解説
-

2025.11.23
【最新版】レバクリの評判や口コミを徹底調査!AGA治療の効果や料金も解説
最新記事
-

2026.02.19
【調査結果】現代人の8割以上が「寝る前スマホ」に罪悪感! 理想の入眠スタイルは「情報の気絶」ではなく「物語への没入」であることが判明
-

2026.02.18
東京でデジタルデトックスをするなら?おすすめスポットと効果的なやり方を徹底解説
-

2026.02.13
紙の本を読むメリットとは?電子書籍と比較して分かる驚きの読書効果と魅力
-

2026.02.10
心斎橋の夜カフェで読書三昧。喧騒を離れて静寂を楽しめる名店選びの極意とは?
-

2026.02.09
新宿の夜カフェで至福の読書タイムを。静かに本を楽しめるおすすめスポットと選び方のコツ
-

2026.02.07
休日を最高にする「ソロ活」の魅力とは?自分をアップデートする究極の過ごし方ガイド
-

2026.02.05
寝る前の読書で人生が変わる?驚きの効果と睡眠の質を劇的に高める秘訣
-

2026.01.21
【クレーンゲーム利用実態調査】「欲しいけど諦める」が41.4%。クレーンゲームの最大の障壁は“取れないこと”ではなく“持ち帰ること”だった?【500人意識調査】
-

2026.01.09
【2026年最新】オンラインクレーンゲームの口コミ・評判を徹底比較!失敗しないアプリの選び方

 就職・転職
就職・転職 